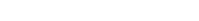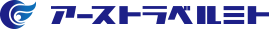【教育現場インタビュー】赤塚中学校・石川校長が語る「変わる修学旅行のカタチ」と教育の原点
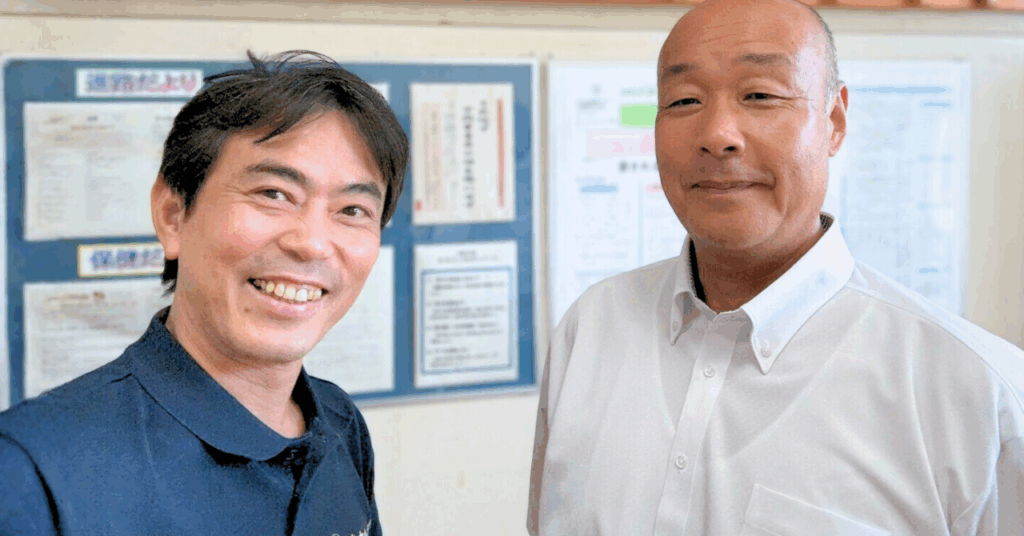
物価高騰や社会の変化を受け、全国の学校で「修学旅行のあり方」を見直す動きが広がっています。行き先や費用だけでなく、子どもたちにとって“なぜ行くのか”という教育的な意味が、いま改めて問われています。
関東地区公立中学校修学旅行委員会の役員を務める、水戸市立赤塚中学校・石川 聡校長は、そうした変化を現場の最前線で感じているひとりです。
アーストラベル水戸代表の尾崎が、教育旅行の実情とその教育的な価値についてお話を伺いました。
物価高騰のいま、修学旅行をどう続けるか
尾崎:最近、修学旅行費の高騰が全国的に話題になっています。水戸市でも見直しの動きがあると伺いましたが、現状をどのように感じていらっしゃいますか?
石川校長:宿泊費や交通費がどこも上がっています。今のまま続けることもできますが、その分ご家庭への負担が大きくなります。旅行会社さんも努力してくださっていますが、限界があるように感じます。
尾崎:地方の小さな学校では、人数や費用の関係で、旅行会社に依頼が難しくなるケースもあると聞きます。
石川校長:そうなんです。東北新幹線や北陸新幹線の利用がしやすい他県では、旅先を東北や北陸に変える学校もありますが、茨城の場合は一度東京を経由しなければならず、交通費や時間も余計にかかることが考えられます。
だからこそ従来の行き先とともに新たな行き先にも目を向けながら、今後の修学旅行を検討する機会があってもよいと感じます。費用や移動時間、子どもたちにとってどんな学びがあるか、を総合的に考える必要がありますね。
教科書を飛び出し、実物が語りかける学びへ
尾崎:教育旅行の価値については、どのようにお考えですか?
石川校長:まずは「思い出づくり」という側面が大きいですね。友達と親元を離れ、計画から実行まで関わる中で、自分で考えて行動する力が育まれます。
そして社会科の教員としての視点から言えば、「実物を見る」ことの価値は計り知れません。教科書で見る大仏と、実際に見上げる大仏はまったく違います。「昔の人はどうやって作ったのだろう」という驚きや感動は、実際に体験しなければ得られません。
清水寺の舞台や龍安寺の庭園など、昔の人の知恵や文化に直接触れることで、学びたいという気持ちが生まれるんです。
尾崎:まさに「体験が記憶を超える瞬間」ですね。
石川校長:ええ。知識だけでなく、五感で感じて学ぶことが大切だと思います。
パナマでの経験が育んだ、言葉に宿る“重み”
尾崎:先生はパナマで教員をされていたと伺いました。
石川校長:はい。25年ほど前にパナマ共和国で4年間、現地に住む日本の子どもたちに教えました。パナマでの生活の中で、貧困からくる厳しい現実を前に、「生きた学び」の重要性を痛感しました。
尾崎: 教科書では伝えきれない“現実”ですね。
石川校長:そうです。銃を持った警備員や高層ビルの傍で物乞いをする人がいる社会を体験し、日本を外から見つめ直しました。日本の生徒たちに、現地で見聞きした貧困の中で、生活のために厳しい選択をせざるを得ない子どもたちの話をしたことがあります。彼らはその話を聞いて、皆、言葉を失いました。実際に見てきたからこそ、伝わるものがあるんです。
尾崎:先生の言葉の重みが違いますね。
石川校長:教育旅行も同じです。未知の環境に触れることで、自分の当たり前を見つめ直す。それが「旅の教育力」です。
尾崎: 「旅が教えてくれるのは、知識ではなく“視点”」という言葉を思い出します。
“信頼”と“信念”を胸に、先生方と歩む校長という仕事
尾崎:石川校長先生は、日々のお仕事の中で、どんな魅力ややりがいを感じていらっしゃいますか?
石川校長:校長という仕事は、日々が学びの連続ですが、その分大きなやりがいを感じています。 その原点を思い返すと、やはり担任だった頃の経験があります。
当時は「こんな気持ちにさせたいな」という思いを込めて子どもたちと接していました。子どもたちがその思いに応えてくれることが、私にとって何よりのギフトでしたね。校長になった今は、その思いを担任の先生方を介して子どもたちに届けることができます。
先生方が自ら考え、行動することで、子どもたちも応えてくれます。そのやりとりこそが先生自身の成長につながる、と私は思っています。私が前に出過ぎると先生方の思いが伝わらなくなってしまうので、 「先生ならどうしたい」と声をかけながら、見守るようにしています。
尾崎:ご自身の考えを押し付けるのではなく、先生方が自ら考えるように促すスタイルですね。
石川校長:はい。また、私は指導の際にいつも“信念”を大切にしています。たとえば、子どもを指導したときに保護者から「なぜそんな指導をしたのですか?」と聞かれたとしても、「この子にこうなってほしいから、こういう指導をした」という確固たる思いがあれば、ブレることがありません。
尾崎:なるほど。その思いが伝われば、きっと保護者の方も納得してくださいますね。
石川校長:そうなんです。たとえ一度で理解されなくても、「自分の思いをちゃんと伝えきれなかったことが申し訳なかった」と正直に話せばいい。そうすることで、逆に信頼関係が生まれると信じています。
育てる教育から、未来をつむぐ教育へ
尾崎:アーストラベルでは「地域創生と教育の両立」をテーマにしています。茨城の子どもたちが都会に出ていく現状を、どう感じていらっしゃいますか?
石川校長:教育現場でも大きな課題です。優秀な人材を育てる一方で、その多くが都会へ出て行ってしまう。もちろん、都会で活躍するのも素晴らしいことですが、地元で育った子どもたちが、その活躍の場をどうしても都会中心に求めてしまうという構図は、地方が抱える共通の悩みです。
尾崎:そうですよね。だからこそ私たちも、教育旅行を通じて“地元を知る・好きになる”体験を増やしていきたいんです。茨城にも、子どもたちが誇りを持てる場所や仕事がたくさんありますから。
石川校長:それは本当に素晴らしいことです。教育と地域がつながれば、子どもたちの人生の選択肢が広がると思います。応援しています。
尾崎:校長先生のお言葉、大変励みになります。本日は貴重なお話をありがとうございました。
インタビュー後記:旅が育む「生きる力」
石川校長先生からお話を伺い、私の中で「旅」と「教育」の根底にある共通点がさらに明確になりました。それは、教科書の中だけでは決して得られない“実物に触れる学び”です。
大仏を前に抱く驚き、海外で目にした社会の現実。五感と体験から生まれる“生きた知恵”こそが、教育旅行の本質だと改めて確信しています。そして、その原点には、現場の先生方が子どもたちに「自分で考え、たくましく生きていく力を育みたい」と願う、熱い思いがあることを深く感じています。
私たちアーストラベル水戸は、そんな教育現場の皆様の思いに寄り添いながら、子どもたちの未来を育むお手伝いをしていきたいと考えています。これからも、地域と教育のニーズに応える体験学習プログラム「シゴトリップ」を提供してまいります。
⚫︎アーストラベル水戸について知る
⚫︎シゴトリップやアーストラベル水戸について動画で知る
⚫︎職場体験プログラム「シゴトリップ」について知る