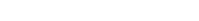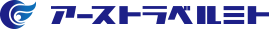大規模校の挑戦と革新的な取り組み
つくば市立学園の森義務教育学校・永井校長先生インタビュー
つくば市で1700人という大規模校を運営する学園の森義務教育学校。その永井校長先生に、アーストラベル水戸の尾崎が現在の教育現場の課題や独自の取り組みについてお話を伺いました。
大規模校運営の現実と工夫
尾崎:永井先生、今日はありがとうございます。1700人という大規模校の運営で苦労されることはありますか?
永井校長:教職員一人一人が組織の一員として機能するように、一人一人の「よさ」を把握することです。そして、教職員も150名規模になると、埋もれがちな人材の発掘や適材適所の配置を大切にしています。また、一部の教職員の考えで物事が進まないように、若手・中堅・ベテランの世代間コミュニケーションに配慮して、日々の打ち合わせや情報共有を徹底しています。さらに、経営には「100人の壁」という言葉がありますが、私を含め教育活動の核となる教職員のマネジメント力の向上も重要視しています。
尾崎:校長先生ご自身はどのような関わり方を?
永井校長:できるだけ細部にわたって私の考えが伝わるように、多くの職員との対話を大切にしています。提案や新しい取り組みは、教職員に「ねらい」を明確に示すとともに、「見通し」がもて、活動に主体的に取り組めるようにすることや「楽しそう」と感じられるような雰囲気づくりと根回しを重視しています。また、教職員のワークライフバランスにも配慮して、柔軟な勤務体制や業務分担を実施しています。
尾崎:先生方との距離感も大切ですね。
永井校長:チームで仕事をする上で、仕事を円滑に進めていくためには、互いの意思疎通はとても重要です。だから若い先生たちには、先輩の先生たちの名前や顔を覚えることが一番大切だと言っています。それが一番わかりやすい仕事の基本です。意思疎通が図られていれば、仕事が円滑に進むことが多いと思います。実は、私自身も、この学校に来た時は150名の教職員の名前を必死で覚えました。大規模組織ゆえの情報伝達・意思疎通の難しさを、日々の打ち合わせでカバーするように心がけています。
教育方針:「しなやかさ」と「たくましさ」
尾崎:学園の森の教育方針について教えてください。
永井校長:本校では、義務教育学校の利点を生かし、認知・非認知能力の育成を系統的に行っています。特に、「たくましさ(未来をたくましく生き抜く力)」と「しなやかさ(予測困難な時代を柔軟に対応する力)」の両輪で人間力を高める方針を取っています。具体的には、非認知能力の育成に際しては、「身に付けさせたい力」を明確にした教育活動に主眼を置いています。授業だけでなく、特別活動、体験活動、校外学習、ICT(AIを含む)の利活用等を推奨し、「たくましさ」や「しなやかさ」を併せ持った子どもたちの育成に取り組んでいます。
尾崎:具体的にはどのような体験活動に取り組まれているんですか?
永井校長:デジタル化が進む中で、アナログな体験の価値を再評価することを重視しています。社会や理科の体験学習、系統的なキャリア教育等、多岐にわたる取り組みを行っています。校外学習の意義を「教科学習の深化」と「人間力育成」の両面で捉えて、9年間のカリキュラム全体でバランスを取ることを意識しています。
最近の外部活動事例
尾崎:外部との連携について、具体的にはどのような取り組みをされていますか?
永井校長:移動博物館の開催(県自然博物館)や証券会社による金融教育プログラムなど、体験型学習を重視した取り組みを重視しています。また、職場体験学習も従来と異なる業種や場所への派遣を積極的に行っています。
尾崎:先生向けの取り組みもあるんですね。
永井校長:教師として力量をあげるために、つくば市、筑波大学、近隣の学校等との連携した取り組みを積極的に行っています。外部資源に恵まれている地域なので、その利点を生かし、研修にも力を入れています。本日も校内研修に外部の方を招聘し、学園生の意識調査の分析の仕方について助言をいただいています。
尾崎:教科書会社を呼ぶという発想がすごいですね。
永井校長:教科書って、中身は教育関係の大学の先生が作るけど、デザインやイラストは教育畑じゃない人が関わってるんですよ。その専門の人たちに現場を見せることも大切だと考えています。また、組体操などのチャレンジ活動も、リスクをきちんと説明した上で実施しています。安全管理と説明責任は徹底していますが、子どもたちの「たくましさ」を育てるためには必要な活動だと考えています。
尾崎:外部との連携でのメリット、デメリットは?
永井校長:私は、「プラス思考」なので、よさが分かる見通しがもてれば、連携を強化していきたいと考えています。当然、外部資源を活用しなければ、打ち合わせの時間もあまりかけないですみますが、教育活動が「前例踏襲型」に陥りやすいです。だからこそ、教育目標の達成に向けて意義のある教育活動には、前向きにチャレンジしていきたいと考えています。
受験による生徒流出への対応
尾崎:義務教育学校でも受験で出ていく生徒がいるんですか?
永井校長:これが一番の課題ですね。6年生の約1/3が外部受験をして、約40名が外部進学してしまいます。進学志向や受験率の高さ、外部進学の傾向を踏まえて、学校独自の魅力発信が急務だと感じています。
尾崎:どのような対策を考えていますか?
永井校長:義務教育学校なので、小学校と中学校の「切れ目」のない教育活動を展開することができます。子どもたちの「学びをつなぎ、心をつなぐ」教育を行えるような、カリキュラムづくりや教育環境づくりが大切だと考えます。今まさにその仕組みを作っているところです。受験する私立学校との違いを明確に打ち出していくことが重要だと思っています。
尾崎が心に残ったこと
今回のインタビューで最も印象深かったのは、永井校長先生の現実的で戦略的な学校運営の姿勢でした。
特に心に残ったのは、「たくましさ(未来をたくましく生き抜く力)」と「しなやかさ(予測困難な時代を柔軟に対応する力)」の両輪で人間力を高めるという教育方針です。デジタル化が進む中でアナログ体験の価値を再評価し、金融教育や移動博物館、職場体験など、多様な体験活動を9年間のカリキュラム全体でバランスよく配置する戦略的な視点は、現代の教育現場に必要な考え方だと思います。
また、外部連携の多様性にも感銘を受けました。先生向けには、出版会社による研修、児童・生徒向けには移動博物館や証券会社による金融教育プログラムなど、ターゲットを明確にした連携戦略は、学校教育の可能性を大きく広げるものだと感じました。
教職員150名という大規模組織での人材マネジメントも印象的でした。埋もれがちな人材の発掘・適材適所の配置、世代間コミュニケーションへの配慮、そして校長自らが現場に出て説明責任を果たす姿勢。これらは組織運営の基本でありながら、実践するのは容易ではありません。
6年生の約1/3が外部受験し、約40名が外部進学してしまうという課題に対しても、現実を受け入れながら対策を練る永井校長先生の姿勢は、多くの学校が直面する問題への示唆に富んでいます。
現実的でありながら、子どもたちの未来を真剣に考える永井校長先生のお話は、教育の本質について多くのことを考えさせてくれるインタビューでした。特に、体験活動が子どもたちの夢やキャリア形成に与える影響の大きさを改めて実感し、アーストラベルとしても教育現場により良いサービスを提供していきたいと強く思いました。
取材協力:つくば市立学園の森義務教育学校 永井校長先生
インタビュアー:株式会社アーストラベル水戸 代表 尾崎