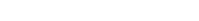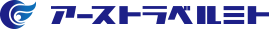先生インタビュー#3~ひたちなか市立大島中学校 長沼先生~
学校現場で働く先生へのインタビュー、第三弾!
今回は、ひたちなか市立大島中学校の教員、長沼純平先生に「先生という仕事の魅力」と「コロナ禍での学校現場の変化」についてインタビューさせていただきました。

【吹奏楽を通して生徒と向き合う】
「小学生のころから学校の先生になりたいという思いがありました。関わってきた先生がよかったのかなとも思います」
学生の頃からの夢である「先生」となった長沼先生。どうして先生という仕事を選んだのか、その理由を伺いました。
「子どもも含めて、人が好きなんです。学校で子どもたちといる時が一番楽しいですね。人と関わり何かすることが好き、という人には合う仕事だと思います」
長沼先生は現在吹奏楽部の顧問を勤めています。自身も学生時代はずっと吹奏楽を続けてきたそう。大学4年生の時には、全日本アンサンブルコンテストで金賞を取るなど精力的に取り組んできました。情熱を持って続けてきた「吹奏楽」を通して、生徒と関わることが本当に好きなのだろうな、とインタビューを通してひしひしと感じてきました。
「スポーツであればレギュラーなどありますが、吹奏楽は30何人全員でひとつのものを作り出さなければなりません。だから、できない子が目立ってしまうんです。そのサポートは難しいけれども、限られた中でどれだけできるか考えていますね」
吹奏楽部の指導では、「応援されるチーム」になるにはどう振る舞えばよいか、という指導に注力しているそう。
「今の中学校の吹奏楽部に赴任した時、まず初めに取り組んだのは挨拶です。2週間で挨拶が本当に変わりました。生活態度の改善もそうですが、チームとして応援されるような立ち振る舞いを生徒たちには考えさせています」
【どうせやるなら本気で】
長沼先生は、生徒には自分としっかり向き合ってほしい、と話します。
「中学生の時期から自分と向き合わず逃げてしまうようだと、将来社会に出た時に大丈夫なのか心配になります。生徒たちが自分と向き合う力を養っていきたいです」
「どうせやるなら本気でやりたいですよね。本気でやらなきゃ物事の本質って見えないと思うんです」
「本気で」この単語がインタビュー中何度も出てきました。長沼先生の教育に対するストイックな姿勢が感じられました。
「手間ひまかけてやらなきゃいけないことってあると思うんです。例えば生徒会選挙がそうでした。アンケートフォームで投票してはどうかという意見が出たんです。でも、実際の選挙は手書きですよね。大人になる過程で、面倒でも大人と同じようなやり方で学んでいくべきだと思います」
「特に、コロナ禍で学校現場でもタブレットが活用されるようになりましたが、(インターネットツールを)使う場面と使わない場面の使い分けが大切だと思います」
【コロナ禍 若い先生が活躍するきっかけに】
コロナの影響で、IT機器を利用する機会が増えました。そういうツールの知識は若い人のほうが詳しいので、若い先生が活躍できたという点ではよかったですね」
若い先生の活躍のきっかけとなった一方、痛手もあったようです。
「吹奏楽部のコンクールもコロナによって中止・延期となり、生徒たちが発表の場数を踏めずに、本番慣れできないという点では影響を感じていますね」
「授業も9月のはじめはオンラインになりました。ずっと家で座って授業を受けているので、生徒たちの体力が落ちているな、という実感があります。」
「オンライン授業では、その時間に何を学んで何をする時間なのかをはっきりさせるように心がけていました」
「授業だけでなく、合唱コンクールにしても修学旅行にしても、それをやる意味は何だろうかと生徒に考えさせることを心がけています。何事も目標を立て、それを実現するためにどうするべきか考えることが大切ですね」
【先生になって10年の節目 大学に入り直して】
長沼先生は昨年の夏、大学に入り直して書写書道教育を学びました。先生としてキャリアを重ねつつ学問を学び直すこともできることに、とても驚きました。
「教員になると、学校の外に目を向けることが難しいです。大学に再び通ったことで、外の情報を吸収するインプットの時間になったと思います」
「やはり、教員と大学生では時間の流れが違うなあと思いました。ひとりの時間が多かったので、本や映像を見たり、趣味にかける時間をとることができました。時間がゆっくりに感じましたね」
【さいごに】
インタビューを通して、とにかくストイックに自分と向き合う先生なのだなあと感じました。大学に入り直すなど常に新しい視点を得ようとする姿勢は、私も見習わなければと気が引き締まりました。自分が中学生の時にこんな素敵な先生と出会いたかったです!
インタビュー/記事 髙橋
撮影 橋本