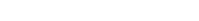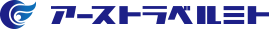“向き不向きより前向き” —信頼と対話で教育現場を輝かせる 東海村立東海南中学校 石川先生
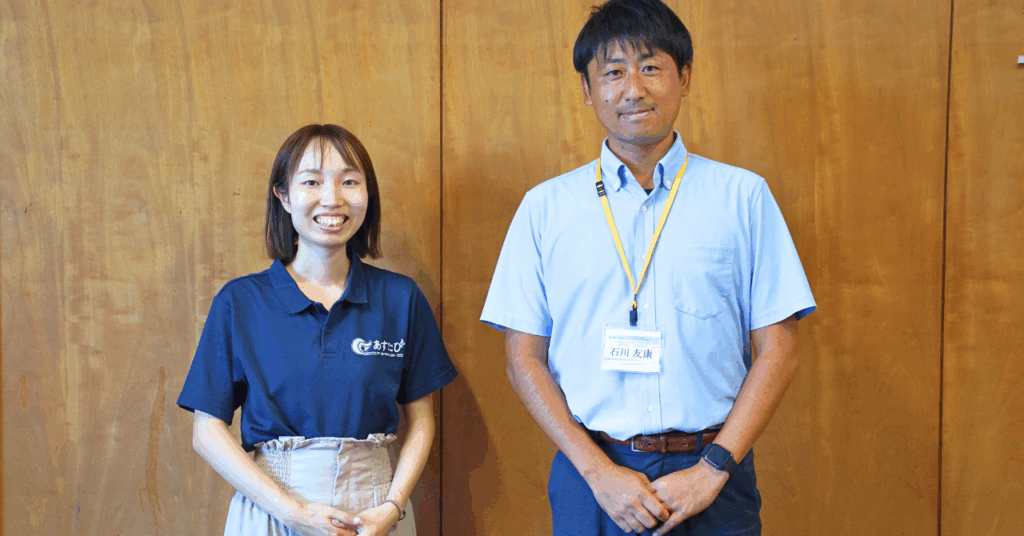
学校現場で活躍する先生のリアルな声をお届けする「先生インタビュー」。
今回は、「子ども中心」の教育への転換、教師同士の関係づくり、そして「前向きさ」を武器に教育現場で奮闘する東海村立東海南中学校の石川先生にお話を伺いました。
失敗も成功も、すべてが糧となる先生の道—その魅力と挑戦に迫ります。
“先生ってカッコいい” ~教師への第一歩を踏み出したきっかけ~
石川先生が先生を志したきっかけは、何よりも父親の存在でした。先生だった父の姿を幼い頃から見て育ち、自然と身近な職業として意識していたといいます。
「父親が先生だったので、小さい頃から先生の姿を見ていました。他の職業を考えてなかったですね。今思えば先生以外にもいろんな職業があるなと思いますが、その時は父が先生だし、周りの先生たちを見て『こういう風になりたいな』と感じていました」
しかし、より大きな影響を与えたのは、自身が出会った恩師たちでした。石川先生は中学時代の担任の先生たちから強い影響を受けたそうです。
「中学校の先生方には本当にお世話になりました。1年生の時の先生は熱血で、学級通信も毎日のように手書きで出していて、人間味があり、怒るときは怒るけど生徒に深く関わる先生でした。3年生の先生は生徒に近くて、なんでも話したくなるような方で、卒業式にはギターを弾きながら涙を流し、一緒に歌いました」
石川先生は、自分が学校生活を楽しめたのは、このように本気で向き合ってくれる先生たちがいたからだと振り返ります。先生たち自身が楽しそうに教育に取り組む姿が、子どもたちにも伝わっていたのです。
人生の伴走者として ~成長の瞬間に立ち会える喜び~
「生徒の成長を感じられた時、一緒に泣いたり笑ったりして活動するとき、そういう時が最も良かったと感じます。文化祭でクラスが団結する瞬間や、クラスマッチで勝って皆で喜び合ったり、何でもない日常の中でも子どもたちの成長を感じる瞬間があります」
特に印象的なのは、卒業後の生徒との関わりです。成長した姿を見られることが、教師冥利に尽きると言います。
「初任者の時の子たちと数年後に飲みに行く機会がありました。その時の喜びは忘れられません。子どもたちの成長を間近で見られることが、先生という仕事の最大の喜びですね」
スーツケースか風呂敷か ~子どもと向き合う姿勢の大転換~
石川先生の先生としての転機は、採用2年目の出来事でした。自身の教育アプローチに行き詰まりを感じた時期だそうです。
「2年目の時に子どもたちの思いにうまく応えられなかった。今思うと子どもを管理していたんです。『こうさせたい、させよう』という意識が強く、ベテラン教師と同じようにさせなければと思っていました。自分中心で、子どもたちを指導するというより『させる』という関わり方だったんです」
この苦しい経験から、石川先生は自分の教育観を根本から見直しました。
「その次の年、小学3年生の担任になった時、『これではダメだ』と思い、子どもたちへの信頼をベースに置き、子どもたちに任せることからスタートしました。子どもたちが主役で、教師は上から見下ろすのではなく、同じゴールを目指して一緒に歩んでいく。生徒が活躍できる場を作り、子どもたちの自己選択、自己決定を促すようになりました」
石川先生は、「スーツケース型」と「風呂敷型」の教育観の違いを例に挙げながら、自身の変化を説明します。
「以前の私はスーツケース型でした。決まった枠の中に子どもたちを押し込もうとしていた。でも本当は風呂敷のように、いろんな形に対応できる柔軟性が必要なんです。子どもたちを包み込むようなアプローチに変えていきました」
教師も”チーム戦”の時代 ~意図的に作る対話の文化~
石川先生は現在、教務主任として、学校全体を見渡す立場になっています。そこで感じるのは、教師同士の関係づくりの重要性です。
「先生たちの関係作りはめちゃくちゃ重要です。私たちの校内研究の一つとして、先生たち同士の関係をよくするための部会を作りました。雑談カフェのように集まって話をしたり、全教師で調理実習をしたり、異年齢、異経験年数、異学年や異教科の先生方が関わる機会として意図的に対話の機会を作っています」
石川先生はサッカーのキャプテン経験から、チームをまとめる力を自然と身につけていたといいます。
「コミュニケーションを取ることを重視し、チームの中で目的意識を共有しながら、同じ方向を向けるようにしてきました。先生同士が仲が良いと、子どもたちもそれを感じ取り、学校全体の雰囲気が良くなります」
特に若手教員に対しては、メンター制を導入するなど、ベテランや中堅が関わる仕組みを作り話しやすい環境づくりを心がけています。
「若い先生には経験のある先生が寄り添い、伴走するような仕組みも作りました。先生同士の対話を増やし、話せる場を意図的に作ることで、学校全体の風土が変わってきます」
教育者としてのモットー ~「向き不向きより前向き」~
石川先生のモットーは「向き不向きより前向き」です。どんな状況でも前向きに捉え、失敗も受け入れて楽しむという姿勢が、教育活動の基盤になっています。
「自分自身、高校受験も大学受験も採用試験も失敗してきました。それを乗り越えてきた経験が今の自分を作っています。母親の前向きな姿勢も大きな影響を受けました」
この前向きさは子どもたちにも伝わり、クラスの雰囲気を明るくします。しかし、石川先生は前向きさを押し付けることなく、一人ひとりの個性に寄り添うことも大切にしています。
「迷った時には『難しい方、自分が成長できる方を選ぶ』というマイルールを持っています。基本的に優柔不断なので、そういうルールがあると選びやすくなります」
毎日がドラマ~退屈とは無縁の教師という仕事~
最後に、石川先生は教師という職業の魅力についてこう語ります。
「子どもたちの人生のどこかに携われているというのは、他の職業ではなかなかないことです。責任は大きいですが、毎日が同じ日はなく、常に子どもたちの成長する場面に立ち会えるのが魅力です」
「幼少期からサッカーを続けているのですが、現在指導するサッカー部が全国大会に出場した時も嬉しい気持ちになりました。」
また、教師自身も学び続ける存在であることを強調します。
「生徒たちから学ぶことも多く、私たち教師も成長し続けられる職業です。子どもたちと共に成長していくことができるのは、この仕事の醍醐味だと思います」
石川先生、お忙しいところ貴重なお話をありがとうございました!
アーストラベル水戸では、教育関係者向けの視察旅行や研修プログラムも企画しています。詳しくはこちらをご覧ください。