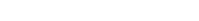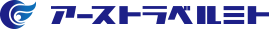先生インタビュー実施!
学校現場で働く先生へのインタビュー、第二弾!
今回は、ひたちなか市立大島中学校の校長、樫村校長先生に「先生という仕事の魅力」と「コロナ禍での学校現場の変化」についてインタビューさせていただきました。

【先生とは人づくりの仕事】
「人と関わり触れ合うことが好きな人にとって、先生という仕事はとても魅力的な職業だと思います」
そう話す樫村先生は、初対面の私にもフレンドリーに話しかけてくださり、きっと生徒にもこんな感じで明るく話しかけてくれる先生なのだろうなと思いました。
生徒に、自分はどんな人なのか考えさせ、そして夢や目標を持たせる。これが先生をしていて1番楽しいところだと話します。
「学習指導、部活動、学校内での普段の生活、これらの支援を通して『夢を持った人』をつくりたいです。しかし、それは昨日今日で作り出せるものではないです。教え子が何年か経って自分の元を訪れた時に立派に成長した姿を見ると、当時は苦労したけれどもやっていてよかった、と本当に思います。」
理科を教えていた樫村先生の授業は、単に教科書通り進めるのではなく、時には雑談を挟むこともあったそう。
「授業のなかで、アインシュタインの相対性理論を噛み砕いて紹介しました。そうしたら、その話がずっと忘れられず、大学院まで進んで物理の研究をしているという生徒がいたんですよ。その生徒からは、『先生の話を聞いていなかったら、今の道に進んでないです。』と言われました。」
「人をつくるということは魅力的ですが、先生の一言で生徒の人生が大きく変わるということもあります。そういう面では責任も大きい仕事です。でも結局は、生徒自身で道を選ばなければなりません。生徒の主体性を大事にしたいです。」
先生が勧めてくれた本や映画は気になって調べていたよなあと、自分の中学時代を思い出しました。思春期に1番身近にいた「先生」という大人の存在はとても大きいのだと改めて実感しました。

【コロナ禍 思うように学校行事が実施できないもどかしさ】
新型コロナウイルスの影響として真っ先に上げたのはやはり、学校行事の中止でした。
「コロナの影響で学校行事ができず、消化不良のような気持ちです。特に昨年は、総体も中止になりました。後輩たちが3年生の戦いぶりを見て、そこから何を学び、何を感じ取るのか、そういう経験ができなかったことは残念です。」
「部活動の大会だけでなく、修学旅行や体育祭、合唱コンクールなど1年の節々にある学校行事を通して、クラスの絆は深まっていきます。行事を経るごとにクラスがまとまり、助け合っていくところを見るのも楽しみのひとつなんですけどね。」
担任を受け持っていた時に印象に残った学校行事として、合唱コンクールの話をしてくださいました。
「練習が始まった頃は、男子が全然歌わなくて本当に大変でした。(笑)そんなにやる気がないなら、うちのクラスだけ放課後練習を無くそう、と厳しめの言葉を投げかけたりもしました。」
「最初は私も練習に関与していましたが、ある時期を乗り越えると生徒が自分たちだけで練習に取り組むようになるんです。歌わない子や歌えない子には、生徒同士で教え合う姿を見ることができました。」
コロナによって、クラスの絆を深める機会が中止や縮小になったのはとても残念ですが、プラスな変化もあったとか。
「今年9月の休校の時期はオンライン授業を導入しました。教科書は進められましたが、生徒がどの程度理解しているのか分からないという不安はあります。ですが、今後必須となるICTのスキルを教員だけでなく、生徒も学ぶことができたという面ではよかったのかな、とも思います。」
【『共に生きる』を実践する場へ】
「我が校のグランドデザインは『共に学び、共に支え、共に生きる』です。学校は、『共に生きる』を実践する場だと思います。」
「クラスという集団のなかで例えば、『あの時あれをやってくれてありがとう』と褒められたら嬉しいものです。こうして自己肯定感を上げていくことができます。また、自分自身が『人の助けになった』と自己有用感を得ることができます。自分を知り自分を好きになることが大切なんです。共に生きることが結果として、学び、支えにも繋がります。」
「共に生きるの実践を指導してくれ、と折に触れて本校の先生方にも話しています。授業で間違えても笑われない、バカにされない、安心して失敗できるような環境をつくりたいですね。」
【さいごに】
「実は私も自己肯定感は低い方です。すぐいじけてしまうんです(笑)」
インタビューの最後、樫村先生はそう仰っていました。自己暗示のような気持ちで、共に生きるを考えているそうです。どこまでも謙虚な姿勢を生徒に見せていて、素敵だなと思いました。何十年もかけて人と関係を築くことができる「先生」という仕事。なぜ、先生の背中があんなにも大きく見えたのかその理由が分かった気がします。
インタビュー、記事執筆:高橋
撮影:橋本